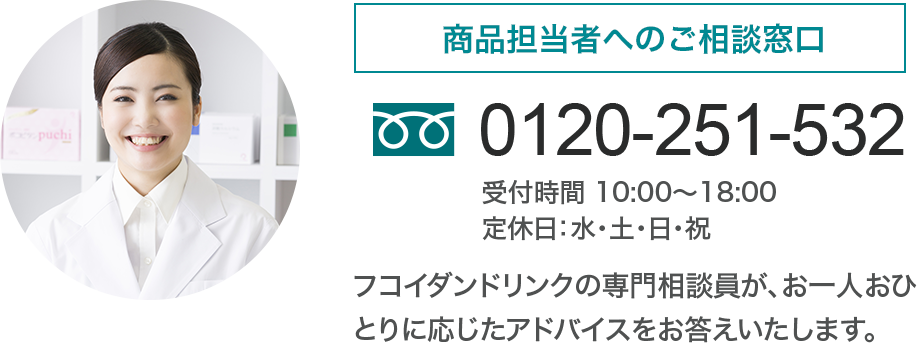海のスーパーフード「海藻」に含まれる栄養素とは?おすすめの食べ方もご紹介
 近年、海のなかで二酸化炭素を吸収する“ブルーカーボン”として世界から注目を集めている「海藻」。地球に優しいだけでなく、栄養価の高さも折り紙つきです。今回は、海藻に含まれる栄養素に迫ります。海藻にギュギュッと詰まった有用成分を効率よく摂取するためのおすすめの食べ方もご紹介するので、参考にしてみてください。毎日、海藻を食べて、美しく健康的な毎日を目指しましょう。
近年、海のなかで二酸化炭素を吸収する“ブルーカーボン”として世界から注目を集めている「海藻」。地球に優しいだけでなく、栄養価の高さも折り紙つきです。今回は、海藻に含まれる栄養素に迫ります。海藻にギュギュッと詰まった有用成分を効率よく摂取するためのおすすめの食べ方もご紹介するので、参考にしてみてください。毎日、海藻を食べて、美しく健康的な毎日を目指しましょう。
海藻とはどんな食材?
 「海藻」とは、海のなかに生える藻類のことです。実は、「海草」とは別のものを指します。 海草は、花を咲かせる海中の植物のことを言い、種子を作って繁殖します(スガモ・アマモなど)。 一方で、海藻は花が咲かない海中の植物を指し、胞子によって繁殖するのです(アオノリ・モズク・フノリなど)。 海藻は色の違いによって「緑藻類」・「褐藻類」・「紅藻類」に分けられます。この色に違いは日光が届く量に左右されるのです。浅瀬になるほど地上の植物の色に近い緑色になり、水深が深くなるにつれ、褐色、そして紅色の海藻が多くなっていきます。
「海藻」とは、海のなかに生える藻類のことです。実は、「海草」とは別のものを指します。 海草は、花を咲かせる海中の植物のことを言い、種子を作って繁殖します(スガモ・アマモなど)。 一方で、海藻は花が咲かない海中の植物を指し、胞子によって繁殖するのです(アオノリ・モズク・フノリなど)。 海藻は色の違いによって「緑藻類」・「褐藻類」・「紅藻類」に分けられます。この色に違いは日光が届く量に左右されるのです。浅瀬になるほど地上の植物の色に近い緑色になり、水深が深くなるにつれ、褐色、そして紅色の海藻が多くなっていきます。
海藻に含まれる栄養素
「ミネラルの宝庫」とも言われている海藻ですが、どのような栄養素が含まれているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。フコイダン
フコイダンとは、モズク・ワカメ・昆布・メカブといった褐藻類の「ぬめり成分」のことです。1913年にスウェーデンの科学者によって発見されて以来、そのパワーに世界中が注目を寄せ、続々と有益な研究結果が報告されています。特に、お酒をよく飲む人などにおすすめの成分です。食物繊維
食物繊維は、人間の消化酵素で分解されない食物中の成分です。体内に吸収されないため、エネルギー源にはなりません。しかし、健康維持のために重要な機能を持っており「第六の栄養素」という異名があるほどです。 食物繊維には「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」があり、海藻類に多く含まれているのは水溶性食物繊維です。 水溶性食物繊維は水に溶けるとゼリー状になり、便を適度な柔らかさに保ちます。 また、粘性のある水溶性食物繊維は胃のなかに入ってきた食べ物をキャッチするため、食べ物が胃から小腸へ移動するスピードが遅くなるのです。その結果、「腹持ちが良くなる」という嬉しい働きもあります。鉄分
鉄分は血液中のヘモグロビンの一部となり、体中に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。食べ物に含まれている鉄分は動物性食品に多い「ヘム鉄」と、植物性食品に多い「非ヘム鉄」に分けられます。 海藻に多い非ヘム鉄は、ヘム鉄に比べて吸収率が劣りますが、ビタミンCやタンパク質と一緒に食べることで、カバーできることがわかっているので、食材の組み合わせに工夫するとよいでしょう。 また、かつては「鉄分の王様」と言われたヒジキですが、製造方法が鉄釜からステンレスを使用して製造されることが多くなった今では、約1/9量にまで減ってしまいました。現在は、青のりや焼きのり・昆布といった海藻のほうが鉄分は多く含まれています。| 海藻名 | 100gあたりの鉄分量(mg) |
|---|---|
| 青のり(素干し) | 77.0 |
| 干しヒジキ(鉄釜) | 58.0 |
| 焼きのり | 11.0 |
| 刻み昆布 | 8.6 |
| カットワカメ(乾) | 6.5 |
| 干しヒジキ(ステンレス) | 6.2 |
フコキサンチン
フコキサンチンは、モズクやワカメ・昆布などの褐藻類に特有の鮮橙色の色素です。人工的に作り出すことができず、海藻以外には含まれていません。甘いものや脂っこいものが好きな人におすすめの成分で、年齢に負けずいつまでもハリのある毎日を送るためにも役立ちます。マグネシウム
厚生労働省による国民栄養調査(2017年)では、多くの日本人がマグネシウム不足だという結果が出ています。マグネシウムは、私たちの体のなかで約50~60%が骨に、残りの40%は脳・筋肉・神経に存在します。体内では、生体維持に必要なさまざまな代謝に関わっています。 ストレスにより尿から多くのマグネシウムが排出されてしまうことが分かっているので、ストレス社会に生きる現代人は、積極的にマグネシウムを補給することが大切です。カルシウム
海藻の中でも特にヒジキ・ワカメ・昆布には、カルシウムが豊富に含まれています。ヒジキを例に挙げると、そのカルシウム量はなんと牛乳の約12倍です。 カルシウムは、私たちの体重のうち1~2%含まれており、体重50㎏の大人であれば約1㎏を占めています。生体内で一番多く存在するミネラルです。そのうち99%は骨や歯に、残りの1%は筋肉・血液・神経などに存在しており、これらの健康維持に欠かせません。リン
リンは、大人の体内に最大で800g含まれていると言われています。その大部分はリン酸カルシウムなどの形で歯や骨を形作っており、カルシウムとのバランスが重要なのです。理想的な比率は、「カルシウム:リン=1:1」と言われています。 しかし、リンは加工食品に食品添加物として広く使われていることから、最近は過剰摂取が懸念されているのです。【海藻100g当たりのカルシウムとリンの含有量と比率】
| 海藻 | カルシウム(mg) | リン(mg) | カルシウム:リン |
|---|---|---|---|
| モズク(塩蔵・塩抜き) | 22 | 2 | 11:1 |
| 乾燥ワカメ(水戻し) | 130 | 47 | 2.8:1 |
| アオノリ(素干し) | 750 | 390 | 1.9:1 |
ご覧のとおり、海藻はカルシウムとリンのバランスが理想に近いものやカルシウムよりもリンのほうが少ないものが多いので、食事全体のカルシウムとリンのバランスを整えるために、海藻料理を添えるとよいでしょう。
ビタミン類
海藻には、ビタミンA・D・Kといった脂溶性ビタミンが含まれています。ビタミンAは、皮膚や粘膜を健やかに保つ役割があり、ビタミンDとKは、カルシウムやリンと相性が良く健康的な体の維持に役立ちます。また、ビタミンKは止血に関わる栄養素です。ヨウ素(ヨード)
海藻は、甲状腺ホルモンを作るために必要なヨウ素(ヨード)を豊富に含んでいます。甲状腺ホルモンは、アクティブな毎日を送るために欠かせないものです。 ヨウ素(ヨード)は私たちが生きていくために必要不可欠なミネラルですが、日本人は海藻を食べる習慣があるため不足する心配は少ないとされています。 特に閉経後の女性では、とり過ぎに気を付けたい成分でもあるので、適量を摂取することを心がけましょう。カリウム
カリウムは、大人の体内に約200g存在しています。多くは細胞内にあり、細胞外液に多いナトリウムと相互に関わり、水分の保持や細胞の浸透圧維持といった大切な役割を担っているのです。 濃い味が好みの人は、カリウムの多い海藻料理も食べるとよいでしょう。EPA
EPAといえば「青魚に含まれるサラサラ成分」というイメージが強いのではないでしょうか。実は、海藻に含まれているEPAを青魚がエサとして食べて蓄えているからこそ、青魚にはEPAが豊富に含まれているのです。 EPAは、体内で作り出すことができないため食べ物から摂取する必要があります。しかし、すべての世代で不足しているため、毎日摂取したい成分です。以上で紹介した栄養素は一部であり、実際は海藻の種類によって、含まれる栄養素や含有量には違いがあります。
健康コラムでは代表的な海藻である「モズク」「昆布」「メカブ」の栄養素について、さらに詳しく解説しています。併せてご覧ください。
モズクに含まれる栄養素について、詳細はこちら
昆布に含まれる栄養素について、詳細はこちら
メカブに含まれる栄養素について、詳細はこちら
健康コラムでは代表的な海藻である「モズク」「昆布」「メカブ」の栄養素について、さらに詳しく解説しています。併せてご覧ください。
モズクに含まれる栄養素について、詳細はこちら
昆布に含まれる栄養素について、詳細はこちら
メカブに含まれる栄養素について、詳細はこちら
海藻のおすすめの摂取方法
 こちらでは、海藻の特性を活かして効率良く有用成分が補給できるおすすめの摂取方法をご紹介します。
こちらでは、海藻の特性を活かして効率良く有用成分が補給できるおすすめの摂取方法をご紹介します。
海藻から食べましょう
甘いものが好きな人や健康を気遣う人は、食物繊維が豊富な海藻を一番初めに食べましょう。食事の初めに海藻のヌルヌル成分で小腸をコーティングするのがポイントです。その次に、タンパク質を多く含む肉や魚、最後に炭水化物を多く含むご飯や麺といった順番で食べましょう。油と一緒に食べましょう
海藻に豊富に含まれる脂溶性ビタミンは、油との相性が良く、油と一緒に食べることで効率的に摂取することができます。また、有用成分「フコキサンチン」は熱に強いので、加熱調理にも向いています。海藻を油で炒めたり、海藻サラダにオイル入りのドレッシングをかけて食べたりしてもよいでしょう。酢と一緒に食べましょう
海藻は酢と合わせることで、柔らかく食べやすくなります。また、酢はフコイダンなどの有用成分との相性が良く効率的に摂取することができるのです。ドリンクで摂取しましょう
健康にうれしいパワーが詰まった海藻ですが、そのまま食べても十分な量を吸収するのが難しい栄養素もあるのです。例えば、フコイダンの摂取量の目安は、一日1~3gが理想的だと言われています。しかし、それを海藻で摂取しようと思うと、昆布やワカメを3㎏以上も食べなくてはなりません。昆布の目安摂取量について、詳細はこちら
また、過剰摂取が懸念されるヨウ素(ヨード)やヒ素などの重金属は無配合で、有用成分だけが濃縮されている点も安心できます。海藻が好きな人も苦手な人も、ドリンクで有用成分を補給するのはおすすめの方法です。
まとめ
海藻に含まれる有用成分をたくさんご紹介しましたが、海藻が“スーパーフード”と言われる理由がおわかりいただけたのではないでしょうか。海草には日本人が不足しがちな成分や海藻独自の貴重な成分が含まれています。海草の特性を理解して、毎日上手に摂取していきたいものです。 しかし、毎日献立を考えて食事で取り入れていくのは簡単なことではありません。また、海藻料理では十分に補給できない有用成分もあります。そんな時には、有用成分が濃縮されたドリンクで手軽に補給するのがおすすめです。ぜひ、海藻の恵みを補給して、美しく健康的な毎日を手に入れましょう。ご提案:集中的にフコイダンを摂取する方法
また、集中的にフコイダンを摂取されたい場合には、 1日あたりの摂取量の目安としてフコイダン1〜3gが望ましいと言われています。 モズクなどの食品から摂取するのはもちろんのこと、 専用のフコイダンドリンクやサプリメントに換算しても 多くの摂取量が必要となってしまい負担が少なくありません。 十分な健康パワーが期待できる中分子フコイダンを効率的に摂取できればその限りではなく、 独自製法によって中分子フコイダンを高配合したメディフコイダンドリンクの場合、 1日あたり1本~3本を目安として摂取してみることを推奨しております。 「いつも元気でいたい」「頑張りすぎている毎日にプラスしたい」という方に、中分子フコイダンという新習慣を提案します。健康パワーだけではなく、女性にうれしい美容パワーも持っているフコイダン。
そんなフコイダンが持つパワーや効果的な摂取方法について、さらに詳しく知りたい方は、以下のコラムもご覧ください。
フコイダンとは!?健康パワーと効果的に摂取する方法を解説!
そんなフコイダンが持つパワーや効果的な摂取方法について、さらに詳しく知りたい方は、以下のコラムもご覧ください。
フコイダンとは!?健康パワーと効果的に摂取する方法を解説!