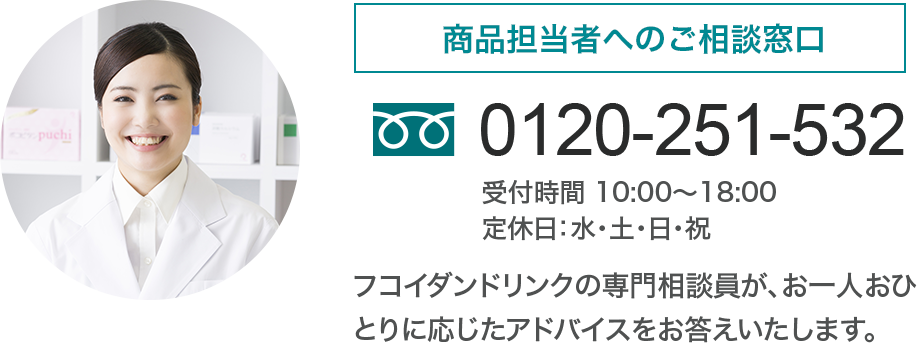もずくの栄養成分とは?一日の摂取量や注意点・効果的な食べ方を解説
 のど越しが良く、さっぱりと食べられるもずくは、「ヘルシーだけどあまり栄養価はなさそう」という印象が強いかもしれません。しかし、そんなイメージに反して私たちが前向きにイキイキと過ごすために一役買ってくれる頼もしい食材なのです。 今回は、もずくの栄養成分や食べるときの注意点・効果的な食べ方について解説します。
のど越しが良く、さっぱりと食べられるもずくは、「ヘルシーだけどあまり栄養価はなさそう」という印象が強いかもしれません。しかし、そんなイメージに反して私たちが前向きにイキイキと過ごすために一役買ってくれる頼もしい食材なのです。 今回は、もずくの栄養成分や食べるときの注意点・効果的な食べ方について解説します。
もずくはどんな食材?
もずくは、昔から全国各地で食べられている海藻の仲間です。数多くの種類があり、食用とされているのは6種類あります。国内では、沖縄県でのみ養殖が成功しており、全国一の生産量を誇っているのです。沖縄もずくは、4月から6月に最盛期を迎えます。もずくの産地について、詳細はこちら
また、世界的にはトンガ王国産のもずくが安全で栄養価が高いことで有名です。トンガは、戦争の歴史がなく、大砲の玉や銃弾が沈んでおらず、とてもきれいな海が広がっています。そんな海で育ったもずくは、高い安全性と豊富なミネラル分が含まれているのです。
トンガ王国産もずくの特徴について、詳細はこちら
もずくに含まれる栄養成分
「もずくはヘルシー」というイメージは強いかと思います。イメージ通り低カロリー(100gあたり6kcal)でありながら、美と健康にうれしい栄養素がギュギュッと詰まった優秀な食材でもあるのです。フコイダン
フコイダンは、海藻特有のヌルヌル成分の一つです。海藻のなかでも「もずく」は圧倒的なフコイダンの含有量を誇ります。なんと、ほかの海藻と比べておよそ5~8倍ものフコイダンが含まれているのです。ミネラル
もずくには、「カルシウム」・「マグネシウム」・「ヨウ素」といったミネラルが豊富に含まれています。詳しく見ていきましょう。カルシウム
カルシウムは骨や歯を形成する材料の一つであり、人体に最も多く含まれるミネラルです。血液や筋肉・神経内にも存在しており、丈夫な体の維持と穏やかな毎日を支えています。マグネシウム
マグネシウムはカルシウムやリンとともに骨や歯を形づくる材料の一つです。筋肉や脳・神経にも存在しており、健康で前向きな毎日を支えています。ヨウ素(ヨード)
ヨウ素は海水のなかに多く存在しているため、もずくをはじめとした海藻や魚介類に多く含まれています。食べ物から摂取したヨウ素は、そのほとんどが甲状腺に取り込まれ、甲状腺ホルモンの構成成分として存在しているのです。 ヨウ素は、健康を維持するうえで欠かせない栄養素ですが、海藻を食べる習慣のある日本人は不足の心配は少なく、摂り過ぎに注意が必要な成分でもあります。
カロテン
カロテンは、黄色や赤色を呈した天然の色素成分です。いつまでも若々しく過ごしたい人は積極的に摂るとよいでしょう。 カロテンのなかでももずくには「β-カロテン」が多く含まれており、β-カロテンは体内でビタミンAに変換されます。ビタミンAは、パソコン仕事をする人やスマートフォン画面をよく見る人におすすめの成分です。健康コラムでは、もずくの健康パワーについてさらに詳しく解説しています。
もずくに含まれる栄養素が、私達の健康にどのような影響を与えるのか、気になる方はぜひチェックしてみてください。
もずくの健康パワーについて、詳細はこちら
また、もずくをはじめとした海藻全般に含まれる栄養素に関するコラムもご用意しています。もずくだけではなく、海藻全般の栄養素について知りたい方は、併せてご覧ください。
海藻に含まれる栄養素について、詳細はこちら
もずくに含まれる栄養素が、私達の健康にどのような影響を与えるのか、気になる方はぜひチェックしてみてください。
もずくの健康パワーについて、詳細はこちら
また、もずくをはじめとした海藻全般に含まれる栄養素に関するコラムもご用意しています。もずくだけではなく、海藻全般の栄養素について知りたい方は、併せてご覧ください。
海藻に含まれる栄養素について、詳細はこちら
もずくを摂取するときの注意
 もずくは栄養豊富でヘルシーな食材だからといって、毎日大量に食べても良いのでしょうか?また、妊娠中は味覚の変化によって食べられない食材が増える人が多いようです。そんなときに「もずくなら食べられる」という人もいるかもしれません。こちらでは、もずくを食べるときの注意点をお伝えします。
もずくは栄養豊富でヘルシーな食材だからといって、毎日大量に食べても良いのでしょうか?また、妊娠中は味覚の変化によって食べられない食材が増える人が多いようです。そんなときに「もずくなら食べられる」という人もいるかもしれません。こちらでは、もずくを食べるときの注意点をお伝えします。
一日の摂取量
もずくは、一日に1パック程度を目安にするとよいでしょう。 もずくには日本人が不足しがちな食物繊維も含まれているため、良い補給源になります。 スーパーなどで売っているもずく酢の1パック(70g程度)はメーカーにもよりますが、調味料を除くとだいたい30~40g程度のもずくが入っているのです。摂り過ぎに注意が必要なヨウ素(ヨード)は、大人では130㎍/日の摂取が推奨されています。
(「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より)
【沖縄もずくのヨウ素と食物繊維の量】
| 沖縄もずく | エネルギー(kcal) | ヨウ素(㎍) | 食物繊維(g) |
|---|---|---|---|
| 100g | 7 | 140 | 2.0 |
| 30g | 2.1 | 42 | 0.6 |
| 40g | 2.8 | 56 | 0.8 |
ヨウ素の摂り過ぎによって健康被害が懸念されるのは、3000㎍/日以上のヨウ素を長期的に摂取するような食生活です。ヨウ素はもずく以外の海藻や魚介類にも含まれているので、その点も考慮すると、一日1パックを目安にするのがよいでしょう。 日本人は海外の食生活に比べて海藻をよく食べる習慣があり、平均で1000㎍~3000㎍/日も摂取していると推定されています。 しかし、毎日の食事で継続的に摂取しているのではなく、たまに海藻や昆布製品を食べるといった家庭が多いようです。海藻が食卓にあがったときのヨウ素量は3000㎍~10000㎍/日ものヨウ素を摂取している場合もあります。しかし、日本人はこのような食生活を送っていても、ヨウ素の摂りすぎによる健康被害はほとんど報告されていません。 そのため、毎日ではなく間隔をあけていれば、余分なヨウ素は排泄されるため、過剰摂取の心配はしなくてよいと考えられています。 また、動物実験の結果により大豆製品に含まれるイソフラボンはヨウ素が体内に蓄積するのを阻害する働きがあることが分かっているのです。そのため、味噌や納豆・豆腐などの大豆製品をよく食べる日本の食生活がヨウ素の過剰摂取による健康被害を回避しているとも考えられ、研究が進んでいます。
妊婦も摂取して良いのか
妊婦や授乳中の人ももずくは一日1パック(調味液を含めて70g程度・調味液を抜いて30~40g程度)を目安にするとよいでしょう。 しかし、妊娠中は特にヨウ素の過剰摂取に対しての体が敏感になっていると考えられています。 同じく、授乳中の女性も母乳中のヨウ素の濃度を過度に高くしないよう気を付ける必要があるのです。 そのため、非妊娠時が3000㎍/日の上限量に対して、妊娠・授乳中は2000㎍/日を超えるヨウ素を継続的に摂取しないよう推奨されています。もずくの効果的な食べ方
 もずくの有用性分を効果的に摂取するために、おすすめの食べ方を3つご紹介します。
もずくの有用性分を効果的に摂取するために、おすすめの食べ方を3つご紹介します。
定番の「もずく酢」
もずくは酢と和えることで、もずくが柔らかく食べやすくなります。また、もずくに含まれるカルシウムは酢との相性が良いので、もずく酢は栄養面からも理にかなった食べ方です。 また、酢に含まれる有機酸はお肉など脂っこい食事を好んで食べる人の健康維持に役立ちます。煮る
もずくの有用成分である「フコイダン」は、水に溶ける性質があるので、煮ることで汁にフコイダンが溶け出し、体に取り入れやすくなります。そのため、煮汁は捨てずに汁物などにして汁ごといただきましょう。食事の最初に食べる
もずくのヌルヌル成分には、消化・吸収されない「食物繊維」が豊富に含まれています。食事の最初に食べることで、腸壁を食物繊維がコーティングしてくれるのです。 また、食物繊維は水に溶けるとドロドロとしたゲル状になるため、食べ物が胃腸内を移動するスピードが緩やかになるため、腹持ちが良くなり、食べ過ぎ防止に効果的です。まとめ
もずくは、ヘルシーでありながら多くの有用成分が詰まっています。海藻のなかでもフコイダンの含有量が圧倒的に多く、積極的に食べたい食品です。 しかし、ヨウ素の摂り過ぎを防ぐには、妊娠している・していないに関わらず一日1パックを目安に食べるのがよいでしょう。 妊娠・授乳中は、特にヨウ素の過剰摂取に体が敏感になっているので、もずくの食べ過ぎには注意が必要です。 ぜひ、今回ご紹介した食べ方を参考に食卓に取り入れてみてください。ご提案:集中的にフコイダンを摂取する方法
また、集中的にフコイダンを摂取されたい場合には、 1日あたりの摂取量の目安としてフコイダン1〜3gが望ましいと言われています。 モズクなどの食品から摂取するのはもちろんのこと、 専用のフコイダンドリンクやサプリメントに換算しても 多くの摂取量が必要となってしまい負担が少なくありません。 十分な健康パワーが期待できる中分子フコイダンを効率的に摂取できればその限りではなく、 独自製法によって中分子フコイダンを高配合したメディフコイダンドリンクの場合、 1日あたり1本~3本を目安として摂取してみることを推奨しております。 「いつも元気でいたい」「頑張りすぎている毎日にプラスしたい」という方に、中分子フコイダンという新習慣を提案します。これまでの研究によると、フコイダンは健康パワー以外に、美容パワーも持つことが判明しています。
毎日を元気に過ごしたい方はもちろん、美しく自信に溢れる姿をキープしたい方にも、フコイダンドリンクはおすすめです。
フコイダンが持つ健康パワーや美容パワーについては、下記コラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
フコイダンとは!?健康パワーと効果的に摂取する方法を解説!
毎日を元気に過ごしたい方はもちろん、美しく自信に溢れる姿をキープしたい方にも、フコイダンドリンクはおすすめです。
フコイダンが持つ健康パワーや美容パワーについては、下記コラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
フコイダンとは!?健康パワーと効果的に摂取する方法を解説!