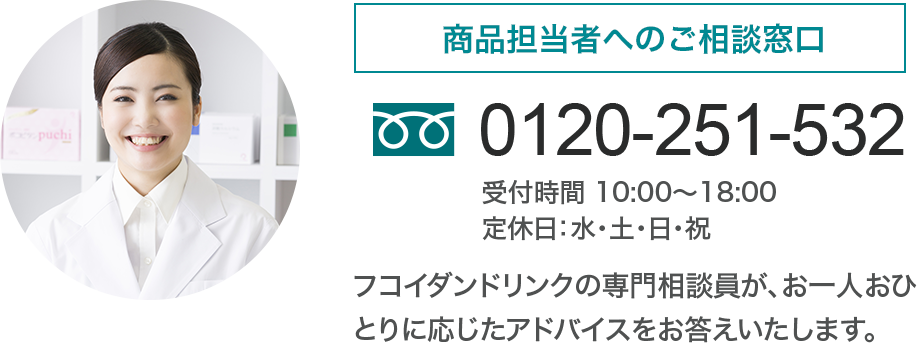体にいい食べ物おすすめ6選。健康に良い科学的根拠も解説

テレビやネットをはじめ様々なメディアで「体にいい食べ物」として、様々な食材・成分が取り上げられています。ただ、本当にしっかりとした科学的根拠に基づいて紹介されているケースは多くはありません。
その一方で、実験や研究の結果、体に良いことがわかってきた食べ物もあります。結局、何を食べれば健康に良いのかがわからない、という方は、今回ご紹介する食べ物を参考にしてみてください。
なぜ食べ物は健康に影響するのか?
私たちの体は食べ物でできているといっても過言ではありません。 食事は基本的に1日3食とるもの。健康で健やかな生活を送るためのベースは食にあるといえるでしょう。
食べ物から各種栄養素やエネルギーを摂取し、生きるために必要な生体活動を行っています。
私たちの生活の質をあげ体を健康的に保つには、やはり体にいい食べ物を選んで食べたいところ。最近の研究で体にいい食べ物や悪い食べ物が科学的に証明されつつあります。
この記事では、エビデンスをもとに提示された「体にいい食べ物、体にいい影響を期待できる食べ物、体に悪い食べ物」をそれぞれ紹介します。
良い健康習慣について詳しく知りたい方はこちら
科学的に証明されている体にいい食べ物6選

飽食の時代になった現代、各種メディアではさまざまな体に影響するいい食べ物や生活を豊かにする食べ物などが多く取り扱われています。いろいろな情報が流通する中、「科学的に証明された体にいい食べ物」が最近注目をあびています。
アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部 准教授であり、医師でもある津川 友介氏によると、信頼性の高い複数の研究結果を取りまとめた結果、ある6種類の食品が不動の「本当に健康にいい食品」に当てはまるそうです。
1つの研究であれば、調査の対象となった特定の国民、または集団にしか認められない結果である可能性が否定できません。
しかし、10や20もの研究が、同じような食事と健康の関係を証明していれば、それはかなり信頼できると言えるでしょう。
以上のような観点から、ここでは津川友介氏によって「科学的に証明された体にいい食べ物」と発表された6種類の食品についてクローズアップし、「体にいい理由」について紹介していきます。
参考:津川友介(2018).『世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事』.東洋経済新報社.
①魚
「魚が体にいい」という根拠はヨーロッパの権威ある栄養学の雑誌※に掲載されました。 信頼性の高い12もの観察研究結果を統合し、合計67万人分のデータを取りまとめることで明らかになったのです。
該当の論文には、1日60gの魚を消費することで、まったく消費しない場合と比較し、死亡リスクが12%減少するという結果が提示されています。
そんな魚に含有されている成分とは
・オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)
これらは多価飽和脂肪酸 に該当し、血液をサラサラにする作用があります。年齢を重ねてもなお健康的な体をキープし、豊かな人生を送るために大切な成分です。
※Fish consumption and all cause mortality: a meta analysis of cohort studies
海藻に含まれる栄養について詳しく知りたい方はこちら
②野菜
野菜と健康の関係については、分析疫学の論文※に記述があります。
追跡調査を行った16の記事を分析し、約83万人分のデータを取りまとめた結果、野菜は摂取すればするほどに「全死亡率(原因にかかわらず死亡する確率)」が減っていく傾向にあることがわかりました。つまりは、健康へのメリットが増えていくのです。
ただし1日5食分(約385〜400g)を超えて摂取した場合、それ以上のメリットは得られないことも明らかにされています。
野菜を食べる際の調理法自体はとくに制限がなく、湯で野菜のように加熱されていてもOKで、冷凍野菜でも加工がされていなければいいそうです。
※Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies
③果物
野菜と同様の論文※では、果物と健康の関係についても言及されています。
同じく16の記事を分析し、約83万人分のデータから得られた結果によると、果物を摂取するほど「全死亡率(原因にかかわらず死亡する確率)」が減っていく傾向にあるそうです。
ただし、こちらも1日5食分(約385〜400g)を超えて摂取したら、それ以上メリットが増えることはありません。
なお、津川友介氏の著書においては、野菜と果物はまとめて1種類に換算されています。野菜や果物を積極的に摂取することは、健康な体を長期間にわたってキープすることに繋がるそうです。
しかしながら、果物に含まれている「果糖」は血糖値をあげるため、糖質を気にしなければならない方は摂取量に注意が必要です。特に果物を使ったフルーツジュースは、できるだけ避けるようにしましょう。
※Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies
④精製されていない茶色い炭水化物
茶色い炭水化物とは、精製されていない炭水化物である「全粒穀物」を指していて、「白い炭水化物」と比較して食物繊維の含有量が多く、ビタミンやミネラルなどの栄養価も豊富です。(※白い炭水化物については、「体に悪い食べ物」の項で詳細を紹介します)
全粒穀物と健康について記されている論文※によると、14の研究を分析し、約78万人分のデータを取りまとめた結果、全粒穀物と死亡率の間には逆相関関係があることが明らかになりました。
具体的には、全粒穀物を積極的に摂取することは早期死亡のリスクを低下させ、長期的な健康に役立つとのことです。
同論文内では、全粒穀物を1日3回以上摂取することが勧められています。全粒穀物は白い炭水化物に比べて体重の増加に繋がりにくいので、ダイエット中の方でも摂取しやすいでしょう。
※Whole Grain Intake and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies
⑤オリーブオイル
「脂肪分は肥満につながるから避けた方がいい」といわれてきた、日本の常識を大きく塗り替えたのがオリーブオイルです。オリーブオイルが体にいいというのは、世界的な医学雑誌に掲載された論文※中に記述されています。
該当の論文によると、オリーブオイルを含む地中海食は血管に対して良好な作用をもたらし、血管のトラブルに起因する死亡率を低下させるとのことです。
この結論はスペインでの多施設共同試験という形で、約7,400人を対象に調査された結果から導き出されました。
またオリーブオイルには、次のような体にいい成分も含まれています。
・一価不飽和脂肪酸
・ポリフェノール
一価不飽和脂肪酸は悪玉コレステロールを減らし、血液の流れをスムーズにしてくれる成分です。ポリフェノールは抗酸化作用が強く、体の酸化を抑制して老化に伴う衰えを軽減してくれます。
※Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet
⑥ナッツ類
ナッツ類も地中海食の一種であり、体にいい食べ物としてオリーブオイルと同じ論文※内で紹介されています。
積極的に摂取することで、オリーブオイルと同様、血管のトラブルに起因する死亡率の低下に繋がるとのことです。
最近はロカボに役立つ食品としても、非常に人気です。カロリーは比較的高めですが、それ以上に、ダイエット中の方にとって嬉しい栄養素が豊富に含まれています。
・不飽和脂肪酸(一価・多価)
・食物繊維
・ビタミン、ミネラル
※Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet
体にいい影響を期待できる食べ物3選

さまざまな「体にいい食べ物」が各メディアで公表されていますが、いまいちエビデンスがハッキリされていなかったり、体に悪い部分に関してフォーカスされておらず、実情がよくわかっていない食品もあります。
ここでは確実ではないものの、「体にいい影響を期待できる」と考えられている食べものを紹介します。
①ダークチョコレート
近年になって体へのよい影響を期待できる食べ物の1つにダークチョコレートがあげられるようになりました。ダークチョコレートは一般的にカカオの含有量が高く、砂糖があまり含まれていない種類のチョコレート。ダークチョコレートの体にいい影響を与える成分として考えられているのが
・ポリフェノール
・カカオニブ由来の食物繊維
の2つです。抗酸化作用の強いポリフェノールは、加齢に伴う体の衰えを遅らせてくれるため、若々しさをキープするのに役立ちます。
カカオニブ由来の食物繊維は、腸内環境を整えるために大事な成分。体の中の不要な物質が、体外に排出されやすくなります。
②納豆
納豆は日本人にとって身近な食品。発酵食品としてヘルシーで高タンパクな食材として昔から人気があります。
納豆にはさまざまな栄養素が含まれており、血流を改善するナットウキナーゼや、抗酸化作用を持つポリフェノールの一種であるイソフラボンなどが有名です。
特にイソフラボンは女性に人気が高い成分で、加齢に伴う女性ホルモンの減少によって引き起こされる不調の改善をサポートしてくれます。
③ヨーグルト
乳製品の消費量と健康の関係について記述された論文※によると、約58万人に対する調査から得られたデータより、ヨーグルトは血糖値の上昇に伴う不調に対して役立つことが明らかにされています。
また、ヨーグルトには乳酸菌やカルシウムなどが含まれています。乳酸菌は悪玉菌の繁殖を抑制し、腸内環境を整えてくれる成分です。カルシウムは骨や歯を丈夫にしてくれたり、神経を安定させてくれたりする成分として有名ですね。
お腹がすっきりすることに関してのサポート食材として古くから注目されているヨーグルトですが、とりすぎによる脂肪の過剰摂取も懸念されている食材です。
※Consumption of dairy foods and diabetes incidence: a dose-response meta-analysis of observational studies
健康的な生活におすすめなもずくの魅力を知りたい方はこちら
体に悪い食べ物はある?
津川 友介氏によると、科学的に体にいい食べ物があるとされている一方で、複数の研究で体に悪影響を及ぼす食品というのも明らかにされています。ここでは、科学的に証明された「体に悪い食べ物」を紹介します。
①牛肉・豚肉・加工肉
世界保健機関(WHO)の専門組織が発表した論文※によると、牛肉や豚肉などの「赤身肉」、加工肉は体に悪い食べ物として考えられています。
赤身肉や加工肉は、どうやら大腸に影響が及ぶようです。摂取量が50g増えるごとに、悪影響も大きくなると言われています。 大腸だけではなく、結腸や直腸への影響も認められています。
唯一、鶏肉だけは赤身肉や加工肉に含まれないため、食事に肉類を取り入れる時は、できるだけ鶏肉を選ぶのがおすすめです。
※Carcinogenicity of consumption of red and processed meat
②白米・うどん
先ほどの項で、茶色い炭水化物(全粒穀物)は精製された炭水化物に比べて食物繊維が豊富とお伝えしました。
一方で白米やうどんなどの精製された白い炭水化物は「食物繊維を極力まで取り除かれ、体の中に糖分として分解吸収されやすい状加工されている」ため、全粒穀物に比べて食物繊維が少なく、相対的に体に悪いと言われています。
また、白米の消費量と健康についてまとめられた論文から、白米の摂取量が増えるほど血糖値の上昇も起こりやすくなることがわかっています。
※White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review
③バター
マーガリンなどのスプレッド系が体に悪いとされ、「代わりにバターを」といわれたこともありますが、バターの消費量と死亡率のリスクに関して論じられた論文※によるとバターも少ないながら、健康に悪影響を与えるそうです。
バターは飽和脂肪酸を多く含んでいます。このことから、摂取量が1日14g増えるごとに、血管に悪影響が及び、血液が臓器へ供給されにくくなると言われています。
また、血液中を流れるブドウ糖の量も増えやすくなるようです。
ただしバターに関しては、同論文にてさらなる調査の必要性があると記述されています。過剰な摂取は避けるべきですが、神経質になりすぎることもないでしょう。
※Is Butter Back? A Systematic Review and Meta-Analysis of Butter Consumption and Risk of Cardiovascular Disease, Diabetes, and Total Mortality
まとめ
さまざまな研究者が私たちの生活の質をあげるために「食べ物」の研究をしています。今後さらなる「体にいい食べ物・体に悪い食べ物」が明らかにされるでしょう。その中からうまく選び出して、バランスを保ちながらよりよい食事を摂取していきたいですね。
食事に気を遣っている方は、もずくを積極的に食べることもおすすめです。もずくに含まれるフコイダンという成分が、健康的に生きたい方に良い影響を与えます。健康面のみならず美容的なサポートにも期待ができるので、メリットも良いです。体にいい食べ物を摂取したいと考えている方は、ぜひフコイダンも取り入れてみてくださいね。
下記の記事では、フコイダンの健康パワーや効果的な摂取法をご紹介しています。ぜひ参考にしながら、今後の食生活にフコイダンを取り入れてみてはいかがでしょうか。